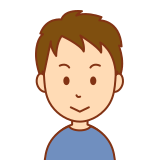
動物たちはどうして私たち人間のように虫歯にならないんだろう?もしかして、歯磨きしなくても大丈夫なのかな?それとも、何か特別な秘密があるのかな?飼っているペットも虫歯になることってあるの?
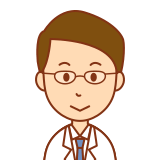
動物が人間ほど虫歯にならない理由はいくつかあり、主に食生活、唾液の性質、歯の構造、そして生活様式に起因します。ただし、「全くならない」わけではありません。特にペットとして飼育されている動物では、食生活が人間化することで虫歯になるリスクが高まっています。
以下に主な理由を挙げます。
1. 食生活の違い
- 糖分の摂取が少ない: 虫歯菌は糖分を栄養源として酸を産生し、歯を溶かします。野生動物は、人間が摂取するような加工された砂糖や炭水化物をほとんど摂りません。
- 肉食動物: 肉や骨には糖分がほとんど含まれていません。
- 草食動物: 草や木の葉、茎などには糖分が少ないです。果物を食べる動物もいますが、人間が食べる加工された甘い果物と比べると、糖分は控えめです。
- 自然なクリーニング効果: 野生動物は硬いもの(骨、木、繊維質の草など)をよく噛んで食べるため、その過程で自然に歯の表面の汚れや歯垢がこすり落とされ、クリーニング効果が得られます。
2. 唾液の性質
- pHの違い: 多くの動物、特に犬や猫の唾液は、人間の唾液(弱酸性〜中性)よりもアルカリ性に傾いています(pH8〜9程度)。虫歯菌は酸性の環境を好むため、アルカリ性の唾液は虫歯菌の増殖を抑制し、酸を中和する効果が高いです。
- アミラーゼの有無: 人間の唾液には、デンプンを糖に分解する消化酵素である「アミラーゼ」が含まれています。これにより、ごはんやパンなどの炭水化物でも口の中で糖が生成され、虫歯菌のエサとなります。しかし、犬や猫などの多くの動物の唾液には、このアミラーゼが含まれていません。そのため、口の中で糖が生成されにくく、虫歯菌のエサが少ない環境になっています。
- 唾液量: 動物によっては唾液の分泌量が人間よりも多く、食べ物の残りカスを効率的に洗い流す効果も期待できます。
3. 歯の構造
- 形状の違い: 人間の奥歯は平らで凹凸が多く、食べかすが詰まりやすい形をしています。一方、多くの動物の歯は、獲物を切り裂くための鋭い尖った歯(肉食動物)や、繊維質の植物をすり潰すための構造(草食動物)をしており、比較的食べかすが溜まりにくい形状をしています。特に肉食動物の犬歯は、歯と歯の間に隙間が広く、食べカスが挟まりにくいです。
- 歯の生え変わり: 多くの動物は人間のように乳歯から永久歯への生え変わりがあるだけでなく、一部の動物(例えば、サメのように生涯にわたって歯が何度も生え変わる動物や、ゾウのように一生のうちに数回歯が入れ替わる動物、齧歯類のように常に伸び続ける歯を持つ動物)もいます。これにより、傷んだ歯が脱落し、新しい健康な歯に置き換わる仕組みがある場合もあります。
4. 自然淘汰
野生動物は虫歯になると、食事を摂ることが困難になり、衰弱して生存競争に不利になります。結果として、虫歯が重症化する前に淘汰されるため、重度の虫歯を持つ個体が少ないという側面もあります。
ただし、虫歯になる動物もいる
前述の通り、完全に虫歯にならないわけではありません。
- ペット: 人間と同じような加工食品や甘いおやつを食べる機会が増えるため、人間と同様に虫歯になるリスクが高まります。特に小型犬などは歯間が狭く歯垢が残りやすいため、虫歯になりやすい傾向があります。
- 動物園の動物: 人間の管理下で甘い果物や加工された餌を与えられることで、虫歯になることがあります。サルやゴリラなどは、人間の食べ物に近いものを食べるため、虫歯が報告されることがあります。
このように、動物が虫歯になりにくいのは、自然な食生活と身体的な特徴が複合的に作用しているためであり、現代のペットのように人間と同じような食生活をすると、虫歯のリスクも高まることがわかっています。


コメント